2024/12/12
再生・細胞医療・遺伝子治療の実用化と産業化の最前線
再生・細胞医療・遺伝子治療は、けがや病気で失われた体の細胞や機能を回復させる、次世代の治療法として、世界中から大きな期待が寄せられています。
日本でも、再生・細胞医療・遺伝子治療の実用化と産業化に向けて、政府や企業、研究機関などがさまざまな取り組みを進めています。
特に経済産業省では、再生医療等製品の製造技術の開発や、原料となる細胞の安定供給などの基盤整備に力を入れています。
また、治験等を通じて有望な再生医療等製品シーズの開発を加速し、産業化を促進する事業も展開しています。
一方、再生・細胞医療・遺伝子治療の普及には、安全性の確保や製造技術の向上、研究開発コストの削減、規制・制度の整備など、まだまだ多くの課題があります。
本記事では、再生・細胞医療・遺伝子治療の実用化と産業化の最前線について、現状や課題、今後の展望を詳しく解説します。
再生・細胞医療・遺伝子治療に関心がある方はもちろん、これからの医療の在り方について考えたい方にも、ぜひ参考にしていただければと思います。
再生・細胞医療・遺伝子治療とは
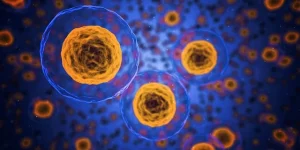
再生・細胞医療・遺伝子治療は、けがや病気によって失われた体の細胞や機能を回復させるための、革新的な治療法の総称です。
従来の治療法では困難だった疾患に対しても、再生・細胞医療・遺伝子治療によって、根本的な治癒が期待できるようになってきました。
ここでは、再生・細胞医療・遺伝子治療の代表的なアプローチである**「再生医療」「細胞医療」「遺伝子治療」**について、それぞれ詳しく解説します。
再生医療
再生医療とは、失われた臓器や組織の機能を再生させる治療法です。
具体的には、幹細胞などを用いて、体外で臓器や組織を培養し、それを患者さんの体内に移植することで、損傷した部位の機能回復を図ります。
再生医療の代表例としては、重症熱傷患者に対する培養皮膚移植や、心筋梗塞後の心機能改善を目的とした心筋再生治療などが挙げられます。
また、iPS細胞(人工多能性幹細胞)を用いた再生医療の研究も盛んに行われており、さまざまな疾患への応用が期待されています。
再生医療は、臓器移植のドナー不足の解消や、移植後の拒絶反応のリスク回避など、従来の治療法の課題を克服する可能性を秘めた画期的なアプローチだと言えるでしょう。
細胞医療
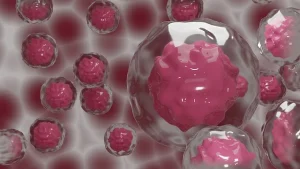
細胞医療とは、特定の機能を持つ生きた細胞を患者さんに投与することで、疾患の治療を行う方法です。
例えば、がん治療の分野では、患者さん自身の免疫細胞(リンパ球)を体外で増殖させ、それを再び体内に戻すことで、がんに対する免疫力を高める「免疫細胞療法」が実用化されています。
また、パーキンソン病などの神経変性疾患に対しては、ドパミン産生能を持つ細胞を脳内に移植する「細胞移植療法」の研究が進められています。
さまざまな種類の細胞を用いた治療法の開発が活発化しており、細胞医療は再生医療と並ぶ重要なアプローチの1つとなっています。
遺伝子治療
遺伝子治療とは、病気の原因となる遺伝子の異常を修復したり、新しい遺伝子を導入したりすることで、疾患の治療を行う方法です。
例えば、先天性の遺伝子疾患である「重症複合型免疫不全症(SCID)」では、造血幹細胞に正常な遺伝子を導入することで、免疫機能の回復が図られています。
また、がんに対しては、がん細胞だけを狙い撃ちできる「がん特異的T細胞受容体遺伝子導入T細胞療法」など、さまざまな遺伝子治療が開発されています。
遺伝子治療は、これまで治療法のなかった難病に光明をもたらす可能性を持っていますが、一方で、倫理的な課題への配慮や、安全性の確保など、克服すべき課題も多く残されているのが現状です。
再生・細胞医療・遺伝子治療は、いずれも従来の治療法の限界を打ち破る可能性を秘めた革新的なアプローチであり、今後のさらなる発展が大いに期待されます。
同時に、これらの先端医療を実用化し、社会に広く普及させていくためには、基礎研究から臨床応用、産業化に至るまでの一貫した取り組みが不可欠だと言えるでしょう。
再生・細胞医療・遺伝子治療の実用化の現状
再生・細胞医療・遺伝子治療は、これまでに数多くの基礎研究や臨床研究が積み重ねられ、いくつかの治療法が実用化されるに至っています。
しかし、その一方で、本格的な普及に向けては、まだ多くの課題が残されているのも事実です。
ここでは、再生・細胞医療・遺伝子治療の実用化の現状について、承認済みの再生医療等製品や実用化における課題、企業の支援の重要性などの観点から詳しく解説します。
承認済みの再生医療等製品

日本では、2014年に「再生医療等製品」という新しい医薬品カテゴリーが設けられ、再生・細胞医療・遺伝子治療に関する製品の開発と実用化が加速しています。
これまでに、以下のような再生医療等製品が承認・上市されています。
【再生医療等製品の主な承認事例】
- ヒト(自己)表皮由来細胞シート:重症熱傷を適応症とする培養表皮
- ヒト(同種)骨髄由来間葉系幹細胞:造血幹細胞移植後の急性移植片対宿主病を適応症とする細胞製剤
- ヒト(自己)軟骨由来組織:膝関節症を適応症とする自家培養軟骨
- CAR遺伝子導入T細胞:再発・難治性の悪性リンパ腫を適応症とするCAR-T細胞療法
このように、皮膚、骨・軟骨、免疫細胞など、さまざまな細胞や組織を用いた再生医療等製品が承認され、患者さんに提供されるようになっています。
今後も、多くのパイプラインが開発中であり、新たな再生医療等製品の上市が相次ぐことが期待されます。
実用化における課題
再生・細胞医療・遺伝子治療の実用化が進む一方で、普及に向けては克服すべき課題が山積しています。
ここでは、技術的課題と法的規制の2つの観点から、実用化における主な課題を整理します。
技術的課題

再生・細胞医療・遺伝子治療の実用化には、以下のような技術的な課題があります。
- 細胞の品質管理:再現性と安定性の高い細胞製剤の製造には、厳格な品質管理体制の構築が不可欠
- 大量培養技術:商業ベースでの安定供給を実現するには、細胞の大量培養技術の確立が必要
- 保存・輸送技術:細胞や組織の長期保存や輸送には、特殊な設備と技術が要求される
- 投与技術:細胞や遺伝子を目的の部位に的確に送達するための高度な投与技術の開発が必要
これらの課題を解決するには、アカデミアと企業の緊密な連携による基盤技術の開発が不可欠です。
また、製造工程の自動化や、周辺機器の開発など、再生医療等製品の産業化に向けた取り組みも重要になってくるでしょう。
法的規制

再生・細胞医療・遺伝子治療には、倫理的な課題も含めて、法的な規制がかかっています。
日本では、「再生医療等安全性確保法」によって、再生医療等提供計画の届出制や細胞培養加工施設の許可制などが定められています。
また、再生医療等製品の製造販売には、薬機法に基づく承認が必要であり、安全性と有効性を確保するための非臨床試験や臨床試験のデータ取得が求められます。
一方、こうした規制の厳格さが、再生医療等製品の開発や上市のハードルを高くしている面もあり、規制当局との適切なコミュニケーションを通じて、開発を効率化していく取り組みも重要となります。
また、グローバルで再生・細胞医療・遺伝子治療の実用化を進めるには、各国の規制当局間の協調や、国際標準の策定など、国際的な取り組みも必要不可欠でしょう。
企業の支援の重要性
再生・細胞医療・遺伝子治療を真に社会実装するには、基礎研究から臨床応用、製品化、市場展開に至るまで、一気通貫の産業化スキームの構築が望まれます。
そのためには、製薬企業やベンチャー企業による積極的な参入と支援が不可欠だと言えるでしょう。
実際、日本では「再生医療実用化研究事業」などの国家プロジェクトを通じて、アカデミアの研究シーズと企業のニーズとのマッチングが図られ、多くの産学連携プロジェクトが進められています。
また、ベンチャー企業の中には、大学等の研究成果を導出して再生医療等製品の開発を手掛ける例も増えてきました。
今後、再生医療等製品の市場拡大を見据えて、企業による製造基盤の整備や、知的財産の確保、レギュラトリーサイエンス人材の育成など、さまざまな支援策を講じていくことが求められています。
また、再生・細胞医療・遺伝子治療のような先進医療技術を国民皆保険のもとで広く提供していくためには、イノベーションの適切な評価と、戦略的な償還価格の設定なども重要な論点となるでしょう。
このように、再生・細胞医療・遺伝子治療の実用化には、まだ多くの課題が立ちはだかっています。
しかし、官民一体となった課題解決への取り組みを通じて、これらの先端医療技術の恩恵を一刻も早く患者さんに届けていくことが、我々に課された使命だと言えるのではないでしょうか。
再生・細胞医療・遺伝子治療の産業化に向けた取り組み

再生・細胞医療・遺伝子治療の実用化を加速し、新たな医療産業として確立するには、基礎研究から実用化、産業化に至るまでの一気通貫の取り組みが不可欠です。
日本では、政府主導のもと、さまざまな施策を通じて、再生・細胞医療・遺伝子治療の産業化を後押ししています。
ここでは、その代表的な取り組みとして、基盤技術開発事業と産業化促進研究開発、社会実装に向けた環境整備について詳しく解説します。
基盤技術開発事業
経済産業省では、再生・細胞医療・遺伝子治療の基盤となる製造技術や創薬支援ツールの開発を支援する「再生医療・遺伝子治療の産業化に向けた基盤技術開発事業」を実施しています。
本事業では、以下の4つの技術領域を重点的に支援しています。
ヒト細胞加工製品製造基盤技術開発
再生医療等製品の製造工程では、原料となるヒト細胞の培養加工が必要不可欠であり、その製造技術の高度化が求められています。
本事業では、大量培養や品質評価などの製造基盤技術の開発を通じて、再生医療等製品の安定供給と製造コストの低減を目指しています。
また、細胞加工のプロセス開発を支援する拠点として、「細胞製造コトづくり拠点」の整備も進めています。
再生医療用原料細胞安定供給研究開発
再生医療等製品の原料となるヒト細胞を安定的に確保するには、細胞の採取・保管・輸送に関する体制の構築が必要不可欠です。
本事業では、医療機関と企業との連携を促進し、採取した細胞を再生医療等製品の製造販売事業者に円滑に提供するための仕組み作りに取り組んでいます。
また、「ヒト(同種)細胞原料供給に係るガイダンス」を策定し、安定供給に向けた具体的な手順や留意点を取りまとめるなど、原料細胞供給の実務を支援しています。
高度創薬支援ツール基盤技術開発
幹細胞等を用いたアッセイ系は、新薬開発の効率化や動物実験の代替など、創薬支援の強力なツールとしても期待されています。
本事業では、iPS細胞等から作成される各種臓器の細胞等を用いて、創薬スクリーニング等に活用できる高度な創薬支援ツールの開発を目指しています。
遺伝子治療製造技術開発
遺伝子治療薬の製造には、ウイルスベクターなどの高品質なツールを効率的に生産する必要がありますが、その製造技術の多くは海外に依存しているのが現状です。
本事業では、治療用ベクターの製造・品質評価技術の開発を通じて、遺伝子治療薬製造のための基盤を国内に確立することを目指しています。
これら4つの技術領域における研究開発の推進を通じて、再生・細胞医療・遺伝子治療の基盤技術の底上げが図られています。
産業化促進研究開発

再生・細胞医療・遺伝子治療の産業化を加速するには、基盤技術の開発に加えて、具体的な治療法の実用化を見据えた研究開発の推進が不可欠です。
経済産業省では、「産業化促進研究開発」と呼ばれる一連の事業を通じて、企業と大学・研究機関とが連携して行う実用化研究を支援しています。
具体的には、再生医療等製品のシーズ開発から非臨床・臨床試験、製造法確立に至るまでの一連の開発プロセスを対象に、重点的な経費補助と薬事・特許等の伴走支援が行われています。
また、再生医療等製品を臨床現場で迅速かつ広範に利用できるようにするため、実用化後の普及・啓発に向けた取り組みも支援の対象となっています。
このように、産業化促進研究開発への支援を通じて、基礎研究の成果を臨床応用につなげ、最終的な製品化を加速する取り組みが進められています。
社会実装に向けた環境整備
再生・細胞医療・遺伝子治療を真に社会実装していくには、研究開発の取り組みに加えて、それを支える社会環境の整備も欠かせません。
そこで、「再生・細胞医療・遺伝子治療の社会実装に向けた環境整備」事業を通じて、再生医療等提供体制の強化と社会受容の促進が図られています。
具体的には、治療効果を科学的・客観的データで確立するための一貫した提供体制の構築や、エビデンスの収集に向けたシステム作りなどが支援されています。
また、再生・細胞医療・遺伝子治療に対する国民の理解と信頼を得るための情報提供や意識啓発にも注力しています。
こうした、安全性と有効性を担保しつつ、社会の理解を深める環境整備は、研究開発の促進と両輪となって、再生・細胞医療・遺伝子治療の社会実装を後押しするものです。
以上のように、日本では、再生・細胞医療・遺伝子治療の産業化に向けて、基礎研究から実用化、普及に至るまでの総合的な取り組みが、官民連携のもとで積極的に進められているのです。
これらの地道な取り組みの積み重ねを通じて、再生・細胞医療・遺伝子治療という新しい治療モダリティが、日本の医療を支える大きな柱に育っていくことを期待したいと思います。
今後の展望

再生・細胞医療・遺伝子治療は、これまでにない革新的なアプローチで、多くの患者さんに希望をもたらす可能性を秘めています。
今後、基礎研究のさらなる進展に加えて、産業化に向けた取り組みが本格化することで、再生・細胞医療・遺伝子治療の実用化はますます加速していくことでしょう。
特に、iPS細胞などの多能性幹細胞を用いた再生医療技術や、ゲノム編集を応用した高度な遺伝子治療は、今後の発展が大いに期待されるところです。
また、これまでは主に難治性疾患を対象としてきた再生・細胞医療・遺伝子治療ですが、今後は、がんや生活習慣病など、より一般的な疾患への応用も進んでいくと考えられます。
ただし、こうした先端医療技術の恩恵を広く国民に届けるためには、安全性と有効性の確保に加えて、コストの適正化や医療アクセスの確保など、克服すべき課題も少なくありません。
産官学が一体となって、こうした課題にも真摯に取り組んでいくことが、再生・細胞医療・遺伝子治療の発展には不可欠だと言えるでしょう。
また、グローバルな観点からも、日本の再生・細胞医療・遺伝子治療が世界をリードしていくためには、国際標準化の推進やグローバル連携の強化など、戦略的な取り組みが求められます。
単に技術的な優位性を追求するだけでなく、世界の医療課題の解決に貢献するという高い志を持って、再生・細胞医療・遺伝子治療のイノベーションを進めていく必要があるのです。
再生・細胞医療・遺伝子治療は、まだ発展途上の分野であり、その実現には多くの困難も予想されます。
しかし、その無限の可能性を信じて、これからも粘り強く研究開発と産業化に取り組んでいくことこそが、私たちに課せられた使命だと言えるのではないでしょうか。
まとめ

本稿では、再生・細胞医療・遺伝子治療について、その概要と実用化の現状、そして産業化に向けた取り組みなどを詳しく解説してきました。
再生・細胞医療・遺伝子治療は、これまで治療法のなかった疾患に新たな光明をもたらす、まさに夢の医療技術だと言えます。
しかし、その実現のためには、基礎研究から実用化、産業化に至るまでの、オールジャパンでの総合的な取り組みが不可欠です。
日本は再生・細胞医療・遺伝子治療の分野で、技術的にも制度的にも、世界をリードする立場にあります。
今後、アカデミアと企業の一層の連携強化や、国民の理解と参画の促進など、多様なステークホルダーを巻き込んだ取り組みを推進することで、再生・細胞医療・遺伝子治療の早期の社会実装を実現していくことが期待されます。
また、再生・細胞医療・遺伝子治療を日本の新たな成長産業に育てていくためには、グローバル市場をも見据えた戦略的な産業政策の推進も欠かせません。
その際、医療分野の産業化というデリケートな問題に対して、倫理的・法的な観点からの慎重な配慮を忘れてはならないでしょう。
再生・細胞医療・遺伝子治療は、次世代の医療を切り拓く日本の重要な資産であり、未来への投資です。
これからも官民学が一体となって、その責任ある発展に向けて、知恵を絞っていく必要があります。
再生・細胞医療・遺伝子治療が私たちにもたらす未来に思いを馳せながら、本稿のまとめとさせていただきたいと思います。
記事監修者プロフィール

資格
- 日本麻酔科学会認定麻酔科専門医
- 日本ペインクリニック学会
- 日本区域麻酔学会
- 日本肥満学会 会員
- 抗加齢学会 会員
- 麻酔科認定医
- 日本心臓血管麻酔学会 会員
- 日本周術期経食道心エコー認定
経歴
- 国立循環器病研究センター勤務を経てLIGHT CLINIC開業
