2025/1/31
再生医療のメリット・デメリット 治療の種類や期待できる効果を解説
再生医療とは
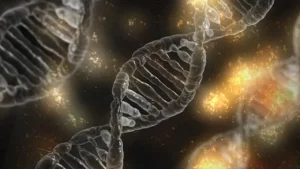
再生医療の定義と歴史
再生医療とは、身体の損傷や疾患によって失われた組織や臓器の機能を、細胞を利用することで再生させる医療のことをいいます。
この革新的な医療技術は、これまでの治療法では助けることのできなかった多くの患者さんに希望をもたらしています。
再生医療の歴史は、1970年代に遡ります。
当時、分化した細胞を培養する技術が確立され、再生医療の基礎が築かれました。
その後、1990年代には「Tissue engineering(組織工学)」という概念が提唱され、細胞と生体材料を組み合わせることで、生体外で組織や臓器を作製する技術の開発が進められてきました。
現在では、再生医療は世界中で活発に研究が行われており、さまざまな疾患に対する治療法の確立が期待されています。
再生医療に活用される細胞の種類

再生医療に用いられる細胞には、大きく分けて3つの種類があります。
それぞれの特徴を理解することで、再生医療の可能性と限界を知ることができるでしょう。
ES細胞
ES細胞(胚性幹細胞)は、受精卵が成長した胚盤胞期の内部細胞塊から樹立される多能性幹細胞です。
身体のあらゆる組織や臓器に分化する能力を持っており、無限に増殖することができます。
しかし、ES細胞の樹立には受精卵を破壊する必要があるため、倫理的な問題が指摘されています。
また、ES細胞は他人由来の細胞であるため、移植した際の拒絶反応が懸念されます。
iPS細胞
iPS細胞(人工多能性幹細胞)は、成体の体細胞に特定の遺伝子を導入することで作製される多能性幹細胞です。
ES細胞と同様に、身体のあらゆる組織や臓器に分化する能力を持っています。
iPS細胞は患者自身の細胞から作製できるため、倫理的な問題や拒絶反応の問題を回避することができます。
しかし、iPS細胞の作製効率は低く、がん化のリスクがあることが課題となっています。
体性幹細胞
体性幹細胞は、成体の組織や臓器に存在する幹細胞で、限られた種類の細胞にのみ分化する能力を持っています。
代表的なものとして、骨髄幹細胞や脂肪幹細胞などがあります。
体性幹細胞は、倫理的な問題が少なく、患者自身の細胞を使用できるため、拒絶反応のリスクが低いというメリットがあります。
また、体性幹細胞は比較的採取が容易で、安全性が高いことが知られています。
しかし、体性幹細胞は増殖能力や分化能力がES細胞やiPS細胞と比べて限定的であるという特徴があります。
現在実施されている再生医療の種類と適応症例

再生医療は、さまざまな疾患や損傷に対して応用が進められています。
ここでは、現在実施されている代表的な再生医療の種類と、その適応症例について詳しく見ていきましょう。
皮膚の再生医療と適応症例
皮膚の再生医療で広く用いられているのが、自家培養表皮移植です。
これは、患者自身の皮膚の一部を採取し、そこから表皮細胞を分離・培養して皮膚組織を作製し、損傷部位に移植する治療法です。
自家培養表皮移植は、重度の熱傷や難治性の皮膚潰瘍などに対して有効性が示されています。
また、先天性の皮膚疾患である表皮水疱症に対しても、自家培養表皮移植が適応されています。
この治療法は、患者自身の細胞を用いるため、拒絶反応のリスクが低いというメリットがあります。
軟骨の再生医療と適応症例
軟骨の再生医療では、自家培養軟骨移植が臨床応用されています。
この治療法は、患者自身の軟骨組織を採取し、そこから軟骨細胞を分離・培養して軟骨組織を作製し、損傷した軟骨部位に移植するものです。
自家培養軟骨移植は、変形性膝関節症や外傷性軟骨欠損などの軟骨疾患に対して適応があります。
軟骨は血管が乏しく、自己修復能力が低いため、一度損傷すると自然治癒が難しいという特徴があります。
そのため、軟骨の再生医療は、従来の治療法では改善が困難だった患者さんに新たな選択肢を提供しています。
心筋への骨格筋を用いた再生医療と適応症例
重症の心不全患者に対して、自己の骨格筋を用いた再生医療が行われています。
この治療法は、患者自身の骨格筋を採取し、そこから筋芽細胞を分離・培養して筋芽細胞シートを作製し、心臓の表面に移植するものです。
移植された筋芽細胞シートは、心臓の収縮力を補助し、ポンプ機能の改善に寄与すると考えられています。
この再生医療は、薬物療法や外科的治療では改善が難しい重症の心不全患者に適応されています。
日本では、2016年から保険適用が開始され、心不全治療の新たな選択肢として期待されています。
間葉系幹細胞を使った再生医療と適応症例
間葉系幹細胞は、骨髄や脂肪組織などに存在する体性幹細胞の一種で、さまざまな組織や臓器に分化する能力を持っています。
この特性を活かして、間葉系幹細胞を用いた再生医療の研究が進められています。
現在、間葉系幹細胞を用いた再生医療は、以下のような疾患に対して臨床応用が進められています。
・脳梗塞
・脊髄損傷
・心筋梗塞
・肝硬変
・膝関節軟骨欠損
・骨欠損
・皮膚潰瘍
間葉系幹細胞は、損傷した組織の修復を促進したり、炎症を抑制したりする効果が期待されています。
また、免疫調整作用を持つことから、移植片対宿主病(GVHD)などの免疫関連疾患に対する治療効果も報告されています。
間葉系幹細胞を用いた再生医療は、低侵襲で安全性が高く、幅広い疾患に対する応用が期待されている分野です。
再生医療のメリット

再生医療は、これまでの医療では治療が難しかった疾患に対して、新たな可能性を開いています。
ここでは、再生医療のメリットについて詳しく見ていきましょう。
疾患の根本的な治療が期待できる
再生医療の大きなメリットの一つは、疾患の根本的な治療が期待できる点です。
従来の医療では、病気の症状を緩和したり、進行を遅らせたりすることが主な目的でした。
しかし、再生医療では、損傷した組織や臓器を再生させることで、疾患の根本的な治療を目指します。
例えば、パーキンソン病などの神経変性疾患では、脳内の特定の神経細胞が減少することが原因で症状が現れます。
再生医療では、失われた神経細胞を再生させることで、病気の進行を食い止め、症状を改善させることが期待されています。
同様に、心筋梗塞や脳梗塞などの虚血性疾患でも、再生医療による組織の再生が治療の新たな選択肢となっています。
拒絶反応や副作用が少ない
再生医療のもう一つの大きなメリットは、拒絶反応や副作用が少ない点です。
臓器移植では、ドナーから提供された臓器が免疫系に攻撃されて拒絶されるリスクがあります。
そのため、移植後は生涯にわたって免疫抑制剤を服用する必要があり、感染症などのリスクが高まります。
一方、再生医療では、患者自身の細胞を使用するため、拒絶反応のリスクが極めて低くなります。
また、幹細胞由来の細胞は、分化した細胞よりも免疫原性が低いことが知られています。
そのため、他人由来の幹細胞を用いた場合でも、拒絶反応のリスクは比較的低いと考えられています。
副作用についても、再生医療では薬物療法と比べて発生リスクが低いとされています。
薬物療法では、全身に薬剤が行き渡るため、目的の臓器以外にも影響を及ぼすことがあります。
再生医療では、治療対象の組織や臓器に直接細胞を移植するため、全身への影響が少なく、副作用のリスクを最小限に抑えることができます。
身体への負担が少ない
再生医療は、外科的な治療と比べて身体への負担が少ないというメリットがあります。
例えば、関節軟骨の損傷に対する従来の治療法では、金属製の人工関節に置換する手術が行われることがあります。
この手術では、健康な骨を削る必要があり、身体への負担が大きくなります。
また、人工関節の寿命は限られているため、若い患者の場合は再手術が必要になることもあります。
一方、再生医療では、患者自身の細胞を用いて関節軟骨を再生させるため、健康な骨を削る必要がありません。
また、再生した軟骨は自然の軟骨と同等の機能を持つため、人工関節よりも長持ちすることが期待されています。
再生医療では、細胞の採取や移植の際に小さな切開が必要になることがありますが、外科手術と比べれば身体への負担ははるかに小さくなります。
薬剤などでコントロールできなかった痛みの改善を期待できる
再生医療は、慢性的な痛みに対する新たな治療法としても注目されています。
例えば、変形性膝関節症では、関節軟骨の磨耗によって激しい痛みが生じます。
従来の治療では、鎮痛剤や消炎剤などの薬物療法が中心でしたが、十分な効果が得られない場合もあります。
再生医療では、損傷した関節軟骨を再生させることで、痛みの原因そのものを取り除くことができます。
同様に、脊髄損傷による慢性的な神経障害性疼痛に対しても、再生医療による治療効果が期待されています。
脊髄損傷では、損傷部位より下位の感覚神経が適切に機能しなくなり、強い痛みが生じることがあります。
薬物療法では痛みのコントロールが難しい場合もありますが、再生医療では損傷した神経組織を修復することで、痛みの改善が期待できます。
再生医療は、これまで治療が難しかった慢性的な痛みに対して、新たな可能性を開いています。
薬剤だけでは十分にコントロールできない痛みに悩む患者さんにとって、再生医療は大きな希望になるかもしれません。
再生医療のデメリット

再生医療は、これまでの医療では治療が難しかった疾患に新たな希望をもたらしています。
しかし、再生医療にはメリットだけでなく、いくつかのデメリットもあることを理解しておく必要があります。
ここでは、再生医療の主なデメリットについて詳しく見ていきましょう。
費用が高額

再生医療の大きなデメリットの一つは、治療費が高額になる点です。
再生医療では、専門的な設備や技術が必要であり、また、細胞の培養や加工にも時間と手間がかかります。
そのため、治療費は従来の治療法と比べて高くなる傾向にあります。
例えば、自家培養軟骨移植は、膝関節軟骨の損傷に対する再生医療の一つですが、治療費は数百万円に上ることがあります。
また、再生医療は保険適用外の自由診療であるため、全額自己負担になることが多いです。
高額な治療費は、再生医療を受けたくても経済的な理由で断念せざるを得ない患者さんもいるでしょう。
再生医療の普及には、治療費の問題は大きな障壁の一つと言えます。
ただし、再生医療の技術が進歩し、治療の効率化が図られれば、将来的には治療費の低下も期待できるかもしれません。
また、一部の再生医療は保険適用になっているケースもあるので、個別の治療法については医療機関に確認する必要があります。
効果を100%保証するものではない
再生医療のもう一つのデメリットは、治療効果を100%保証するものではない点です。
再生医療は、まだ研究途上の分野であり、すべての疾患に対して確実な効果が証明されているわけではありません。
治療効果には個人差があり、症状の改善度合いや持続期間は患者さんによって異なります。
中には、期待したほどの効果が得られなかったり、一時的な改善にとどまったりするケースもあるでしょう。
また、再生医療では、治療後の経過観察やリハビリテーションも重要です。
移植した細胞が定着し、組織や臓器の機能を十分に回復させるためには、一定の時間と適切なケアが必要です。
治療効果を最大限に引き出すには、患者さん自身の努力も欠かせません。
再生医療を受ける際は、治療効果が100%保証されているわけではないことを理解し、現実的な期待値を持つことが大切です。
また、医療機関から治療内容やリスクについて十分な説明を受け、納得した上で治療を受けることが重要です。
治療を受けられるクリニックが限られる

再生医療のデメリットとして、治療を受けられる医療機関が限られている点も挙げられます。
再生医療を実施するには、専門的な知識と技術、設備が必要です。
また、再生医療を行う医療機関は、「再生医療等安全性確保法」という法律に基づいて、厚生労働省に計画を提出し、審査を受ける必要があります。
そのため、現時点では再生医療を実施できる医療機関の数は限定的です。
特に地方では、再生医療を受けられる医療機関が少ないことが多く、治療を受けるために遠方まで通う必要があるかもしれません。
また、再生医療の種類によっては、実施可能な医療機関がごく限られている場合もあります。
例えば、iPS細胞を用いた再生医療は、現時点では一部の研究機関や大学病院でしか行われていません。
治療を希望する患者さんにとって、居住地域に再生医療を実施する医療機関がないことは、大きな障壁となります。
再生医療を必要とする患者さんが、居住地に関わらず平等に治療を受けられる体制の整備が求められています。
行政や医療機関、研究機関が連携し、再生医療の普及と地域格差の解消に取り組むことが重要です。
再生医療に関する法律と課題

再生医療は、患者さんに新たな治療の選択肢をもたらす画期的な医療技術です。
しかし、再生医療を普及させ、より多くの患者さんに届けるためには、いくつかの課題を克服する必要があります。
ここでは、再生医療に関連する法律と、再生医療の発展に向けた課題について詳しく見ていきましょう。
再生医療等安全性確保法と医薬品医療機器等法
再生医療は、患者さんの安全性を確保することが何よりも重要です。
そのため、日本では再生医療に関連する法律が整備され、再生医療を提供する医療機関や再生医療等製品の製造販売業者に対して、一定の基準を満たすことが求められています。
再生医療等安全性確保法は、再生医療を提供する医療機関に対する規制を定めた法律です。
この法律では、再生医療の内容によってリスクを3つのカテゴリーに分類し、それぞれのリスクに応じた手続きを医療機関に義務付けています。
例えば、最もリスクの高い第一種再生医療等については、厚生労働大臣の許可が必要であり、専門的な知識を有する特定認定再生医療等委員会での審査を受ける必要があります。
一方、医薬品医療機器等法は、再生医療等製品の製造販売に関する規制を定めた法律です。
再生医療等製品とは、再生医療に用いる細胞や組織を加工して製造される医薬品や医療機器のことを指します。
この法律では、再生医療等製品の製造販売業者に対して、品質管理や市販後の安全対策などを義務付けています。
再生医療等安全性確保法と医薬品医療機器等法は、再生医療の安全性と有効性を確保するために不可欠な法律です。
これらの法律に基づいて、再生医療を提供する医療機関や再生医療等製品の製造販売業者は、厳格な基準を満たす必要があります。
再生医療等製品の開発・製造コストと人材育成の必要性

再生医療の普及には、再生医療等製品の開発・製造コストの問題も大きな障壁の一つです。
再生医療等製品は、従来の医薬品や医療機器と比べて、開発や製造に多額の費用がかかることが知られています。
特に、iPS細胞など最先端の技術を用いた再生医療等製品の開発には、막大な研究開発費が必要です。
また、再生医療等製品の製造には、無菌環境下での細胞培養など特殊な技術が必要であり、製造コストも高くなる傾向にあります。
高額な開発・製造コストは、再生医療等製品の価格に反映され、患者さんの経済的負担を増大させる要因にもなっています。
再生医療等製品の開発・製造コストを低減させるためには、技術革新や製造工程の効率化などが求められます。
また、再生医療の発展には、専門的な知識と技術を持った人材の育成も欠かせません。
再生医療は、医学や生物学、工学など多岐にわたる分野の知識が必要とされる学際的な領域です。
しかし、現状では再生医療に特化した教育プログラムは少なく、専門人材の不足が指摘されています。
大学や研究機関、企業などが連携し、再生医療の専門人材を育成するための教育体制の整備が急務です。
また、再生医療の臨床応用を担う医療従事者に対する教育・トレーニングの機会も拡充する必要があるでしょう。
再生医療等製品の開発・製造コストの低減と専門人材の育成は、再生医療の発展に向けた重要な課題です。
官民連携のもと、これらの課題解決に向けた取り組みが進められることが期待されます。
まとめ

再生医療は、これまでの医療では治療が難しかった疾患に新たな光をもたらす画期的な医療技術です。
再生医療によって、多くの患者さんのQOL(生活の質)の向上と、医療費の削減が期待されています。
しかし、再生医療にはメリットだけでなく、デメリットもあることを理解しておく必要があります。
再生医療の治療費の高さや効果の不確実性は、患者さんにとって大きな障壁となるでしょう。
また、再生医療を実施できる医療機関が限られていることも、再生医療へのアクセスを妨げる要因の一つです。
再生医療の普及には、こうしたデメリットを克服するための取り組みが欠かせません。
再生医療は、厳格な法規制のもとで実施される必要があります。
再生医療等安全性確保法と医薬品医療機器等法は、再生医療の安全性と有効性を確保するための重要な法律です。
これらの法律に基づいて、再生医療を提供する医療機関や再生医療等製品の製造販売業者は、高い基準を満たすことが求められます。
また、再生医療の発展には、再生医療等製品の開発・製造コストの低減と専門人材の育成が重要な課題となっています。
官民連携のもと、これらの課題解決に向けた取り組みが進められることが期待されます。
再生医療は、まだ発展途上の医療分野ですが、その可能性は計り知れません。
患者さんに新たな希望をもたらす再生医療が、より多くの人々に届けられる日が来ることを願ってやみません。
再生医療の発展には、社会全体での理解と支援が不可欠です。
一人一人が再生医療について正しい知識を持ち、その可能性と課題を理解することが大切だと思います。
記事監修者プロフィール

資格
- 日本麻酔科学会認定麻酔科専門医
- 日本ペインクリニック学会
- 日本区域麻酔学会
- 日本肥満学会 会員
- 抗加齢学会 会員
- 麻酔科認定医
- 日本心臓血管麻酔学会 会員
- 日本周術期経食道心エコー認定
経歴
- 国立循環器病研究センター勤務を経てLIGHT CLINIC開業
